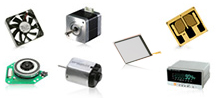現在位置
- ホーム
- 企業・IR・採用
- 採用情報
- プロジェクトストーリー
- 03 スマートライティング市場の創造
このページを印刷する
ここから本文です
Prologue
ミネベアミツミの新型LED照明器具「SALIOT(サリオ)」。薄型レンズに代表される光学技術をはじめ、ステッピングモーター、電源、機構部品など、ミネベアミツミが持てる技術を集約した複合製品だ。配光角(光が広がる角度)を自由に変更でき、向きや色味などを遠隔操作できるSALIOTは、従来の照明の常識を変える製品として注目を浴びている。
しかし、SALIOTが生まれるまで、ミネベアミツミは照明の「素人」だった。照明器具のメーカーでもなければ、自社ブランドによる最終製品を直接市場に問うた経験もない。まさにゼロからのプロジェクトを担った「SALIOT」マーケティングチームは、いかにして市場を開拓していったのか。その道筋は、2015年に大阪から始まった。

小峯 康生
1984年入社 海洋学部海洋科学科 卒業
営業本部照明製品推進統括部責任者。タイやシンガポールなど20年に及ぶ海外駐在から帰国後、マーケティング、広報を経て、2016年からSALIOTの営業販売を担当。

土屋 敦
2001年入社 経済学部経済学科 卒業
営業本部照明製品統括部係長。大阪で照明器具用電源の営業を担当した後、2015年のSALIOT製品化以前よりプロジェクトに携わる。現在は東京を拠点に営業活動を行う。
Chapter 1
ミネベアミツミだからつくれる、
付加価値の高い画期的な照明機器を
「本当にやるんですか……?」―― 土屋は思わずつぶやいた。営業職として、大阪で照明製品の電源部品を担当していた土屋。手元に届いたのは、ミネベアミツミが開発中のLED照明器具の試作品だった。製品化に向けて専業メーカーやユーザーの意見を聞けないか、という開発部門からの依頼だった。ベアリングやモーターなど、製品に組み込まれる「部品」を専門につくってきたミネベアミツミが、照明器具という「完成品」を開発するのは初めてのこと。土屋も戸惑いを隠せなかった。
当時、土屋が扱っていた電源部品は、国外メーカーの参入により価格競争が激化していた。もっと付加価値のある製品を提供しなければ、市場で生き残ることは難しい。そこで着目されたのが、薄型レンズの高い成形技術だ。スマートフォンの液晶画面にバックライトの光を均一に拡散させるための導光板は、ミネベアミツミが得意とする製品。この導光板の成形技術を応用した薄型レンズと、主力製品の一つであるステッピングモーター、そしてもともと照明器具メーカーに販売を行っていた電源を組み合わせる。さらにIoTの技術を使って、手元のスマートフォンから操作可能な「手軽に照射位置の調整ができる照明」のアイデアが生まれたのだ。
高い天井に取り付けられた照明器具は、照らす向きや範囲を変えるだけでも専門の業者に高所作業を依頼せねばならない。遠隔操作で簡単に照明器具を動かすことができれば、早く、安全に、思うままに、照射位置の調整ができるはず。モーターやレンズなど、必要な要素技術は揃っていた。だが、その商品コンセプトは本当に市場に受け入れられるのか? 技術部門が作ったお世辞にもまだスマートとは言えない巨大なプロトタイプを携え、土屋は親しい取引先の担当者を訪問して回った。
「手軽に照射位置を調整できるというアイデアは独創的で、彼らの反応も上々でした。ただ、われわれはレンズやメカには詳しくても、肝心の「光」そのものについては素人。照明のプロの目から見ると、照射面のムラやエッジの形状など、まだまだ不十分な点が多く残っていました。それらの課題を開発部門にフィードバックし、改良を重ねていきました」(土屋)

Chapter 2
1年間で空振り300件の営業活動。
「モノ」ではなく「コト」を商う難しさ
こうして2015年に「SALIOT」が誕生する。引き続き、土屋は大阪でSALIOTの営業を担当するが、大きな壁にぶつかっていた。どの建物にも一般的な照明器具は使われているが、そこにどうやって当社のSALIOTのような付加価値があり、特徴的な照明器具を売り込めばいいのか。その糸口がつかめない。
「ミネベアミツミとして、最終製品を直接ユーザーに売るのは初めての経験です。ビルや商業施設に電話で営業をかけてみても、軽くあしらわれてしまう。部品メーカーとして名が通っていても、当社は照明器具ユーザーの世界では無名でしたから無理もありません。社内でアドバイスをもらえる人間もいませんでした」(土屋)
そこで土屋は、これまで部品を納めていた照明器具メーカーに頼み、営業に同行させてもらうことにした。どこへ行って誰にどう照明器具の良さを訴求するのか、照明業界の営業ノウハウをゼロから学ぶ。まだカタログもなく、商品を解説する1枚のペーパーと重たいデモキットを抱え、手探りの状態で営業に回った。「正直に言えば当時は半信半疑でした。本当に売れるのか?と」。土屋は振り返る。
「部品と完成品では、営業のスタイルが大きく異なりました。部品は納入先から要求されたスペックを満たすことがまず最優先。しかし今回は『この製品によって何ができるのか』を、相手の使い方を考えながらアピールしなければなりません。単に『動かせる』というだけでは説得力が弱く、照明を手軽に動かせることで、どんなことができるようになるのか、どんな心地よい光環境を作り出すことができるのかを説く必要がありました。使い方の提案ですから、正解は一つではない。『モノ』ではなく『コト』を売る難しさを実感しました」(土屋)
300件近くの商談をこなしたが、成約に至らない日々が続く。気がつけば、1年あまりが経過していた。

Chapter 3
明かりのプロに向けて広く情報を発信。
約2年をかけ照明士の資格も取得
小峯がSALIOT担当に加わったのは、2016年のことだった。マーケティングや広報の経験を積んできた小峯は、SALIOTのバリューを広く知らしめることに注力した。
「まずは存在を知ってもらうため、PR活動を展開しました。営業から、お客様がよく読む雑誌について教えてもらい、業界誌に記事広告を出稿するなどしました。また、関連業界の展示会にも積極的に出展しています。ホテル、ギャラリー、建築など、照明に対してアンテナが高い業界の人々に向けて広く発信していきました」(小峯)
SALIOTは徐々に照明の世界で認知されるようになり、コンセプトや実際の動きについては「画期的だ」と高い評価を得た。しかし一方で、照明デザイナーからは光の質に対して厳しい意見も寄せられた。「市場に出し、目の肥えた一流のユーザーの目にさらされたことで、いくつもの新たな発見があった」と小峯は語る。
「私たちも、いつまでも素人ではいられません。私と土屋は足掛け2年をかけて照明士の資格を取得しました。照明業界における標準的な資格であり、彼らプロと同じ土俵で会話をするには必要不可欠だと判断したのです。照明についての『共通言語』を獲得し、知見を蓄えていきました」(小峯)

Chapter 4
当初反対したショールームの開設。
会社の「本気」に背筋が伸びる
大阪から東京へ異動となった営業土屋とマーケティング戦略を担当する小峯を中心に、SALIOTの拡販を担うチームが本格的に動き出した。照明業界出身者のキャリア採用も行い、組織の強化も図った。そして、東京本部のすぐ近くにSALIOT専用のショールームを開設することが決まった。ショールームのデザインを依頼したのは、国内外で活躍するインテリアデザイナー、森田恭通氏。その森田氏によって手がけられた空間は、金色のフィルムに包まれたような他に類を見ないデザインだった。
「われわれが見慣れた工業部品のショールームを想像していたので、最初にデザイン案を見たときは、社長含め全員でひっくり返りました(笑) じつは当初、私はショールームを作ることに大反対したんです。まだ事業として成り立っていません、と。ところが、それに対するトップの言葉は『だから作るんだ』だったのです。そのときハッとしました。必要なタイミングで必要な投資を決断する。新しい市場を創ろうという会社の『本気』を見て、背筋が伸びる思いでした」(小峯)
全員が度肝を抜かれたデザインがそのまま採用されたSALIOT高輪ギャラリーは、2017年の秋にオープンした。空間には、ホテル・美術館・小売店のフロアなど4つのエリアが再現され、天井に設置された200台を超えるSALIOTによって、自由自在に光の演出を変えることができる仕組みが整えられた。その後、年間約4000人の業界関係者が訪れることになるギャラリーの開設を機に、SALIOTマーケティングプロジェクトは徐々に軌道に乗り始める。

Chapter 5
初の大型受注は一流百貨店の旗艦店。
検証を重ね、世界初の売り場を実現
そんな中、ついに初となる受注案件がまとまった。伊勢丹新宿本店へのSALIOT導入だ。売り場に陳列した商品をより魅力的に見せ、購買へとつなげるVMD(ビジュアル・マーチャン・ダイジング)の一環としてSALIOTが採用されたのだ。設置台数全58 灯に及ぶ大型案件、それも一流百貨店の旗艦店での採用。要求されるレベルも高いが、それ以上に業界の注目度も高い。ここで結果を出さねばならない。
「数え切れないほど打合せを繰り返しました。閉店後の店内で幾度となく検証を行い、テナントの従業員さんからも使い心地についてヒアリングして、光の色合いなど細部の調整を施していきました」(土屋)
最終的に足かけ1年以上の期間を要し、SALIOTが導入された世界初の売り場が完成した。
この百貨店の売り場ではほぼ毎週、陳列された商品が入れ替わる。照明を変えるには、そのたびに専門業者へ依頼する必要があったが、SALIOTの導入により営業時間内でも光を調節できるようになった。照らす場所、強さ、色合いなども、各ブランドのカラーに合わせて空間を演出できる。まさに「モノ」ではない「コト」の付加価値を実現した一例と言えるだろう。
「大阪で営業を始めた頃を考えると、ここに至るまでは険しい道のりでした。しかし、こうして実際にSALIOTが設置され、従来の照明とは違う価値を提供できたことは大きな喜びです。達成感でそれまでの苦労も吹き飛ぶ思いでした」(土屋)
売り場でのSALIOTの評判にも後押しされ、その後、導入事例は日本はもとより、東南アジアやアメリカを含め、世界で200案件を超えた。

Chapter 6
奥深い照明の世界を、さらに追求する。
SALIOTがスタンダードになる日に向けて
「東京国立博物館で開催された、フィラデルフィア美術館との交流企画の特別展の照明にSALIOTを使っていただきました。実際に展示を見に行った社員からは、『あんな素晴らしい場所に自社の製品が使われていて嬉しかった、誇らしく感じた』という声がいくつも届きました。そんな言葉をもらって、ここまでやってきて良かったと、私たちも同じ気持ちになりました」(小峯)
ブライダル会場、カーディーラー、ホテル、博物館――。洗練された光が求められる場は、世の中に数多くある。しかし「照明はいたるところにあるが、どこにでも売れるわけではない」と、小峯は気を引き締める。
「それぞれに見合った付加価値を見極めること、そしてなにより、光の質を追求することを忘れてはなりません。照明の世界は奥が深く、まだまだ探求が必要。最適な光学的特性を研究するため、最近では開発部門のメンバーにお客様の環境を見てもらうことも少なくありません。次の世代、またその次の世代までを視野に入れて新製品の開発を進めています」(小峯)
かつて、照明は白熱光からLEDへ大きな変化を遂げた。同じように「光の革命」をSALIOTが成し遂げるかもしれない。土屋はSALIOTの将来に期待を寄せる。
「携帯電話だって、昔は単機能で肩にかけるほど大きかったものが、今や皆スマートフォンを当たり前に使いこなしています。『スマートライティング』を標榜するSALIOTが広く世の中に普及して、いつか『照明器具って昔は、脚立に登ったり、直接触ったりしてライティングを調整していたんだよ』と言われるようになるのが夢です」(土屋)
照明の未来を変える「チームSALIOT」の挑戦は、まだ始まったばかりだ。

本文の終わりです